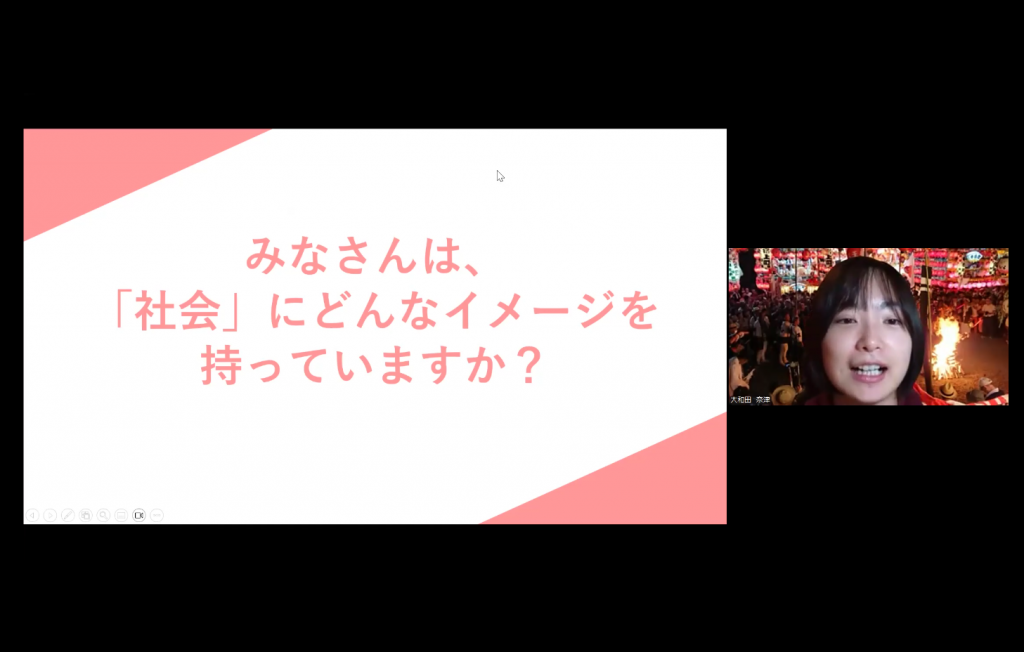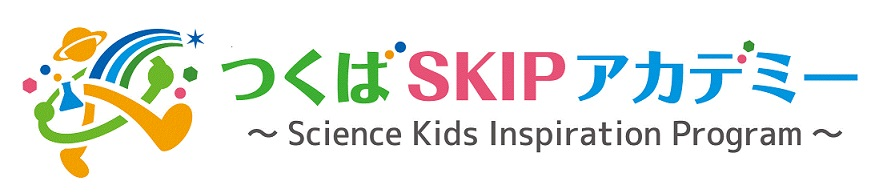サイエンスカフェを開催しました<2025.10.24>
2025年10月24日(金)、サイエンスカフェを実施しました。講師は、千葉大学大学院の大和田 奈津 さんにお願いしました。
大和田さんは茨城県のご出身で、幼少期から地域の祭礼活動(お囃子・太鼓)に参加してきた経験をもとに、社会学の視点と地域社会のつながりについてお話をくださいました。
まず、前半は「社会学とは何か」について解説いただき、
・社会の構造や仕組みを、人の行為や関係から明らかにすること
・“当たり前”を問い直し、多様な立場から社会を捉え直すこと
・地域・世代・ジェンダーなど複数の視点を交えて、暮らしや生き方を考えること
などを挙げていただきました。
続いて、事例として、講師が研究対象としてきた茨城県中市の祭礼が紹介されました。
この祭礼は三年に一度、地域の家々と結びついて運営されており、「効率が悪く見える活動」がなぜ続くのかという問いから分析が始まったことが説明されました。
大和田さんは、地域共同体の絆や家の名誉、女性や子どもの参加の広がり、行政との関わり(政教分離の問題を含む)など、祭礼が社会の変化を映す鏡であることなどを解説してくださいました。
さらに、大和田さん自身の経験として、学校では話せなかったことが祭礼の場で表現できたこと、東京に進学してからも地域に関わり続けたことが紹介されました。これらの経験が研究テーマとつながり、「地域に根ざした学び」が学問の出発点となったことが語られました。
また、質問パートでは、「社会学は何に役立つのか」「転勤が多い社会で地元を持つ意味」「研究と地域活動の両立」などの質問が寄せられました。大和田さんは、人間の行動や社会の仕組みを多面的に考えることが、どの分野でも生きる力につながること、そして学問的視点は“効率”では測れない価値を見いだす営みであることを伝えていました。
参加者は、社会を一面的に見ず、多様な立場から考えることの大切さや、地域行事や伝統文化に、社会を理解する手がかりがあることなどについて、理解を深めることができました。