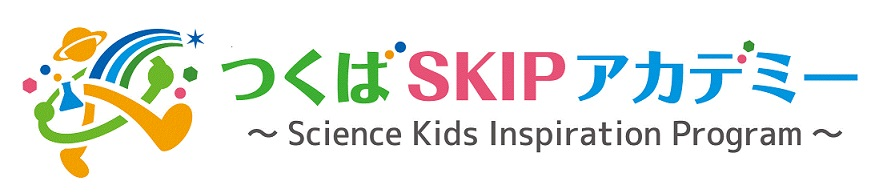サイエンスカフェを開催しました<2025.8.22>
2025年8月22日、サイエンスカフェを開催しました。本講座は、面白い作品や展示に「出会う」ための視点と、その体験を創作・研究のアイデアへと結び付ける手順を学ぶことを目的としました。講師は稲田 和巳さん(筑波大学大学院)にご担当いただき、実例紹介と対話を交えつつ進行しました。
前半は、発想の源となるインプットの捉え方に焦点を当てました。稲田さんからは、優れたアウトプットは「膨大で多様な経験(インプット)」に支えられていること、そして勉強(知識)だけでなく実地の経験を増やすことが重要であると示されました。特に、偶然の出会いを引き寄せる「セレンディピティ」を高めるために、自分の専門外も含め幅広い領域に触れること、さらに「自分は何のどこが好きか」を言語化して感度を上げること、得た刺激を自分の表現へ昇華させるまでの“寝かせる時間”を確保することの三点が強調されました。
後半は、「どこを見るか/どう観察するか」という展示の見方に触れました。作品そのものだけでなく、置き方・距離・光・空間の使い方といった展示設計(キュレーション)を読むことで、作品の個性が最大化する仕掛けを見抜けることが解説されました。具体例として、東京都現代美術館や十和田市現代美術館の展示から、さらにはホームセンターの売り場に作品を置く大胆な試みなど、場所選び・場づくりの力が示されました。映像展示については、六本木アートナイトで屋外LEDと多層スピーカー群で体験設計した事例を取り上げ、「作品の特性から最適な“体験”を逆算する」視点の重要性が共有されました。
終盤では、展示空間の文章(作家自身のステートメント/館の解説文)を読み分ける意義が述べられました。作家が目指す世界観や、館がその展示を今ここで行う理由を掴むことで、作品理解が立体化すること、そして自分で書く立場になった際にも簡潔かつ的確な言葉を選ぶ素地となることが示されました。講座のまとめとして、①多様な対象への継続的アクセス、②「好き」を成分分解して言語化する習慣、③インプットが自分の表現へ変質するまでの時間設計などについて、教えていただきました。
参加者は、展示を「鑑賞する」だけでなく「読み解き、設計し、次の創造へつなぐ」ための具体的な視点を得ることができました。本講座で得た知見は、今後の見学・調査・制作・発表準備において、問い—根拠—答えを明快に結ぶ発信力と、発想を豊かにする観察力の双方を支える土台となると思います。