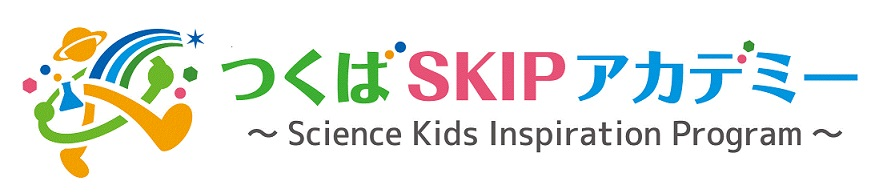2024年度第6回サイエンスカフェを開催しました<2025.02.21>
2025年2月21日(金)、2024年度第6回サイエンスカフェを開催しました。今回は、筑波大学人文社会系・谷口洋子教授を講師にお迎えし、「研究って何だろう―考古学が明らかにする私たちの歴史」をテーマにご講演いただきました。
講演では、まずイタリア・マントバ出土の男女抱擁人骨の写真を提示し、人間同士の愛情表現と「いつから殺し合いが始まったのか」という問いを投げかけられました。狩猟採集期から農耕定住期への移行が争いを生んだという教科書的常識に疑問を呈し、歴史を学ぶ意義を改めて問い直しました。続いて、現代のパレスチナ・イスラエル紛争やシリア・エブラ遺跡のくさび形文字文書の流出事例を通じ、文化財や歴史的記録が政治・民族問題と深く結びつく実例を提示されました。
さらに、日本列島における戦争遺跡として、13,000年前のアフリカや紀元前6000年フランスの集団殺戮墓、吉野ヶ里遺跡の首なし人骨などを紹介し、“いつから人は人を殺すのか”を考古学的証拠から明らかにしました。一方で、シャーマンや再分配・共宴による戦争回避の可能性や、紀元前6000年の立派な介護社会の痕跡を示し、人間社会の現状と考古学との関わりについても学習することができました。
後半では、タンパク質分析やラマンスペクトル法を駆使した、茨城県産の埴輪に使われた青色顔料の最先端研究成果が披露されました。石炭由来のタールから抽出されたアズレン類が、国内で初めて青顔料として利用されていた可能性など、多様な事例が紹介されました。
質疑応答では、「歴史を消す意図は何か」「歴史学習の意義」「文理融合の難しさ」など、多岐にわたる質問が寄せられ、谷口教授は「失敗を知り傲慢にならないため」「昔の知識の凄さを知るため」など、様々な切り口で回答をしていただきました。
当日は、参加者から「従来の“教科書知識”への疑問を刺激された」「文化財保護と現代問題の関連性が理解できた」「茨城の青顔料研究が面白かった」との声が寄せられ、考古学が現代社会と密接に結びつく学問であることを再認識する機会となりました。