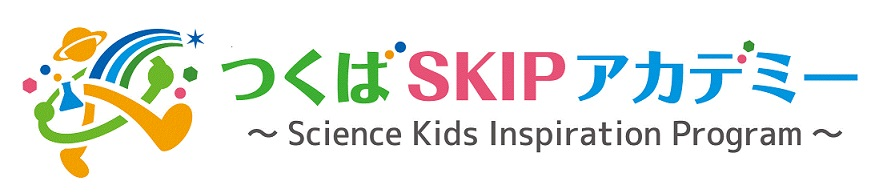「発表資料の作り方講座」を開催しました<2025.8.25>
2025年8月25日、オンラインで「発表資料の作り方講座」が開催されました。本講座は、研究発表の基本構造からポスター・スライドの具体的な作成技法までを扱い、受講生が自らの探究成果を客観的に伝える力を養うことを目的としました。講師は、筑波大学大学院の鈴木 泰我さんにご担当いただき、講義と質疑を交えた形式で進められました。
前半は、研究発表の意義とゴールに焦点が当てられました。鈴木さんからは、「研究は発表して初めて完成する」とメッセージが伝えられ、聞き手が誤解なく一義的に理解できる構成の重要性が強調されました。具体的には、背景・目的・方法・結果・考察・結論の流れに沿って、時系列の出来事をそのまま並べるのではなく、問い(目的)—根拠(方法・結果)—答え(結論)を一直線に結ぶ“論理構造”へ再編する手順が解説されました。また、身近な題材を用いた事例により、目的の立て方と結論の対応関係(問いに対して明確に答えること)の大切さが示されました。
後半は、発表形式とデザインの実践に進みました。口頭発表とポスター発表の違い(前者は定められた順序で通しで語る形式、後者は対話的・自由進行で要点の即時把握が重要)を踏まえ、レイアウトの原則と三つの技術「コントラスト(強弱の付与)」「グルーピング(意味のまとまりの可視化/整列)」「イラストレーション(図解での説明)」が具体例とともに紹介されました。さらに、仕上げ段階で確認すべきポイントとして、可読性(全ての文字が読めるか)、不要要素の排除(意味のない図や写真の撤去)、問いと結論の対応の再点検が提示され、グラフ表現では軸名・単位・体裁の明示によって主張が一目で伝わるよう整える実践的な工夫が示されました。
講座の終盤には、筑波大学SKIP事務局より、夏休み個人研究発表会(9月14日開催)に向けた具体的な案内が行われました。スターターコースはA3縦のポスターによる発表(発表時間5分)、アドバンスコースはスライド発表(目安10枚、発表5分・質疑4分)とし、順位付けや表彰は行わず、質問と助言の獲得を主眼とすることが示されました。
参加者は、論理構造に基づく発表設計の重要性と、視覚デザインの基本技術が理解を促進する効果を再確認しました。今回の学びは、9月の発表会準備のみならず、今後の探究活動における「問い—根拠—答え」を明快に結ぶ発信力の基盤となる機会となりました。